示談書とは?法的効力と記載事項、注意点についてFPが解説
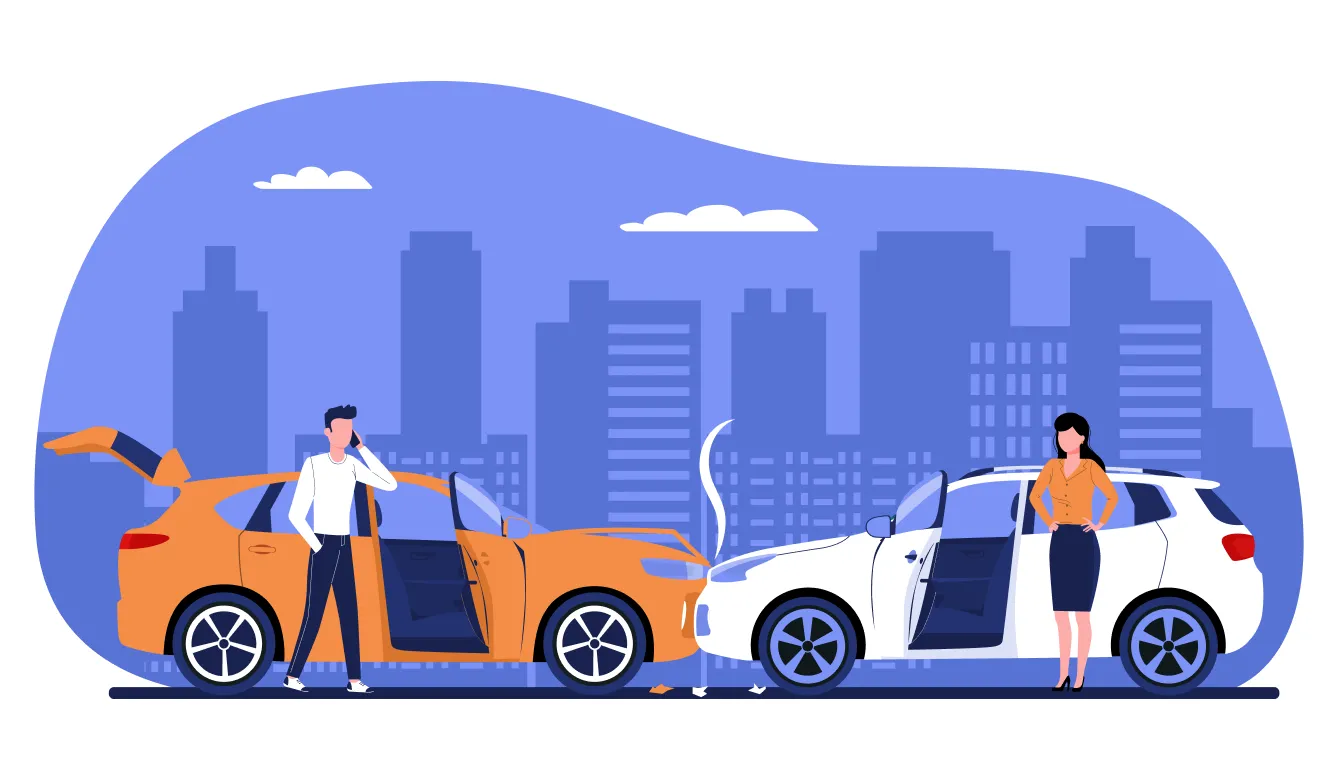
交通事故では、解決方法を口頭で約束すると、後にトラブルに発展する可能性があります。このようなときに重要になるのが「示談書」です。示談書とはなにか、どのようなことが記載されるのかなど、示談書の内容や作成方法、注意点について解説します。
示談書とはトラブルの当事者間で合意した解決内容を記載した書面
示談とは、当事者間(加害者と被害者)に起きた何らかのトラブルについて、裁判をすることなく解決するために話し合うことを言います。お互いが譲歩して、争いをやめることを約束することから、法律上では「和解契約」に該当します。
示談書は、その当事者間の話し合いによって、合意した内容をまとめた書類のことです。交通事故に限らず、損害賠償などの民事上のトラブル解決を目的として作成されます。示談書には法的な拘束力があります。
一般的に、示談書は当事者双方が署名・捺印をして作成し、それぞれ一部ずつ保管します。その内容は、当事者双方が十分に確認し、納得した上で合意することが重要です。
示談書を作成する目的
示談書を作成する目的は、当事者間の合意内容を明確にし、その内容をまとめた文書を残すことで、後のトラブルを減らすことです。口頭でも示談は成立しますが、記録を残さずに口頭で合意してしまうと、後から「言った」「言っていない」など、認識のずれが起きる可能性があります。そのため、合意内容を書面で作成し、その内容を証明することが示談書の重要な役割となっています。
また、示談書は、裁判に比べて時間や費用をかけずに、早期にトラブルを解決できるメリットがあります。トラブルの解決のために訴訟を起こす方法もありますが、裁判では手続きの流れ上長期化する可能性があり、解決内容も法律や過去の判例に則った型通りのものになりがちです。
示談なら、トラブルを円満に早期解決できる可能性が高く、必要以上の手間や時間をかけずに済みます。また、解決内容も互いの合意によって柔軟に決めることが可能です。
示談書の法的効力
示談は、冒頭でも述べたとおり、和解契約(民法695条)とされるため、示談書は契約書としての法的拘束力を持ちます。示談書に署名・捺印し、示談が成立すると、加害者は示談書に記載された示談金(損害賠償金)を支払う義務を負います。
また、示談が成立すると、原則として後から合意内容を変更することや撤回することはできず、示談内容以外の賠償請求もできません。もしも、相手方が合意内容を守らず、トラブルが再燃して裁判になった場合には、示談書を当事者間の合意内容を示す証拠書類として提出することができます。
示談書と公正証書の違い
示談書と公正証書では、記載形式や証人、執行力の有無などに違いがありますので、その内容を理解しておきましょう。
示談書
示談書は、当事者同士が合意した内容を作成し、署名・捺印で確定する文書です。記載方法や内容については特に決められた形式はなく、互いが納得した内容であれば有効になります。
ただし、示談書はあくまで当事者間の合意に基づいているため、第三者の証明がありません。そのため、相手が合意内容を守らない場合などで訴訟を起こしたときは、勝訴後の裁判所での強制執行のために、別途手続きや時間がかかります。
公正証書
公正証書は、法務大臣が任命した公証人が作成するもので、信頼性が高く効力が強い公文書です。公証役場で本人確認を行い、公証人が作成した文書に署名・捺印することで、公的な証明力が与えられます。
賠償金の支払いを確実にするためには、公正証書に「支払いを守らない場合は強制執行が可能」(強制執行認諾文言)と記載する必要があります。これにより、公正証書は示談書よりも強い法的効力を持つため、示談内容を守る強制力も期待できます。
示談書と公正証書、それぞれの特徴を簡単にまとめると、示談書は「比較的簡単に作成できるものの、裁判になると手間や時間がかかる」、公正証書は「公証人による公的手続きが必要な分、信頼性と効力が高い」と言うことができるでしょう。
交通事故における示談書の書き方と手続き
具体的な示談書の書き方についても、確認しておきましょう。
記載内容は個別の事案によって異なりますが、ここでは一般的な交通事故での示談書の書き方と手続きの流れについて解説します。
交通事故における示談書の書き方
交通事故の場合の示談書では、大きく2つの内容を記載します(下記の記載例を参照)。
■交通事故における示談書の記載例
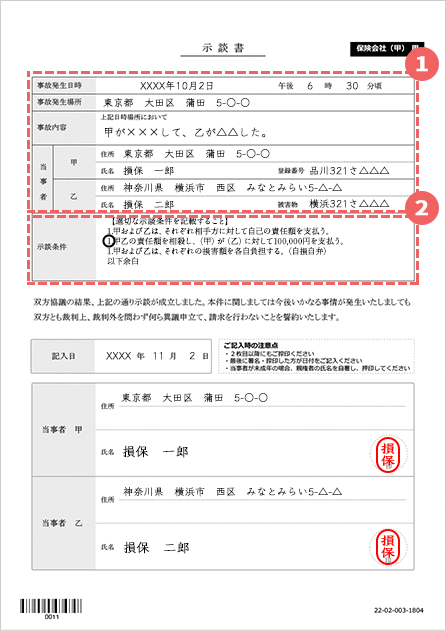
1.事故の事実を記載する項目
- 事故の日時(交通事故証明書に記載の日時)
- 事故の場所(交通事故証明書に記載の場所)
- 事故の内容(追突、出会い頭の衝突など事故の状況)
- 当事者それぞれの住所、氏名、車の登録ナンバー(運転者と車両所有者が異なる場合は、車両所有者の住所・氏名も必要)
交通事故証明書は、警察に事故の届出後、事故現場の各都道府県にある交通安全運転センターに申請すると発行されます。示談交渉を保険会社が行う場合には、保険会社の担当者が取付けを行うため、自身で取付ける必要はありません(駐車場や私有地で起きた事故等、交通事故証明書が発行されない場合があります)。
2.示談内容、支払方法、支払金額などを記載する項目
事故内容にもとづいた過失割合や合意した示談金額、賠償金の支払方法(一括または分割)、支払期限などを記載します。支払方法は、互いに自分の支払額を相手側に支払う方法と、支払額を相殺して支払う方法があります。
交通事故における示談書の手続き
交通事故で、示談書を取り交わすまでの流れについても、押さえておきましょう(下図参照)。交通事故では、事故の当事者が任意保険(自動車保険)に加入している場合、示談交渉は一般的に保険会社が行います。
■示談書を取り交わすまでの流れ
1. 保険会社が示談交渉
当事者が任意保険に加入している場合は、保険会社が示談に向けて交渉します。
2. 保険会社が示談書を作成して被害者へ提示
示談交渉がまとまると、保険会社が示談書を作成し、被害者に提示します。
3. 被害者が内容を確認して署名・捺印
被害者が示談内容を確認し、納得できたら示談書に署名・捺印します。
4. 加害者が内容を確認して署名・捺印
相手方の保険会社を通じて、加害者が示談書に署名・捺印します。
5. 被害者・加害者それぞれで示談書を保管
被害者と加害者、それぞれが示談書を1通ずつ手元に保管します。
なお、被害者の過失割合がゼロの場合は被害者側の保険会社は示談交渉できません。過失割合が100:0の事故の場合は示談書ではなく免責証書という書類を用いるケースが多く、原則加害者側の保険会社が作成します。このような事故で被害者となった場合、保険会社は示談交渉できませんが、交渉を進めるにあたっての相談はできるため活用してください。
任意保険に加入していない場合や、任意保険を使わずに示談する場合には、示談書の雛形を参考に作成すると良いでしょう。
- ソニー損保より補足説明
- ソニー損保の示談書の雛形は以下リンクからダウンロードできます。
示談書のひな形(テンプレート)をダウンロード(PDF)
交通事故における示談書作成の注意点
示談書は、和解のための契約書です。原則として後から内容を変更することはできません。そのため、示談書は内容を慎重に精査したうえで対応することが必要です。示談書を作成するにあたっての、注意点についても押さえておきましょう。
示談書の内容変更は原則できない
交通事故でケガを負った場合、事故当初は何も症状がなかったとしても、時間の経過とともに痛みが出てくることや、後遺障害が発生する可能性もあります。いったん示談書に署名・捺印してしまうと、原則として後から内容の変更はできません。また、特別な記載がなければ賠償請求もできないため、最終的な損害が確定した段階で、示談を行うことが重要です。
示談を急いでしまうと、被った損害の一部しか示談内容に反映されず、損害賠償の額が本来よりも少なくなってしまう可能性があります。ケガがある場合には、治療が終わったあとに示談書を作成するようにします。なお、ケガが完治せず後遺障害が認定された場合は、後遺障害を含めた示談書の内容にする必要があります。
なお、自分の過失が0の場合、加入している保険会社は示談交渉できませんが示談交渉についてアドバイスを受けることはできます。交渉を進めるにあたって不安なことや困ったことがある場合は相談に乗ってくれるので活用すると良いでしょう。また、保険会社以外にも法テラス(日本司法支援センター)など第三者機関での相談も可能です。
示談金は総額で記載される
示談書では、一般的に示談金(加害者と被害者の双方が合意して最終的に支払われる賠償金)は総額で記載されます。大切なのは、総額だけを見るのではなく、その内訳も必ず確認することです。
示談金に含まれるものとしては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などが代表的なものです。被害者の損害は多岐にわたることが多いので、示談金の内訳については必ず精査するようにしましょう。また、示談金の支払方法や支払期限についても、明示されているかどうかも確認したいポイントです。
清算条項を慎重に検討する
示談書における清算条項とは、紛争の蒸し返しを防ぐため、当事者間で示談した後は一切の請求をしないことを確認・約束するものです。一般的に、示談書に記載される条項の1つで、「被害者は示談の成立後、加害者に対して一切の請求をしない」などのような文言で明記します。
ただし、示談書に清算条項を記載すると、後から後遺障害が発生した場合などでも、追加で損害賠償請求ができなくなります。こうしたことを防ぐために、清算条項には「後遺障害が発生した場合には、その損害賠償について別途協議を行う」といった文言を、「留保条項」として記載します。留保条項の記載があれば、清算条項を入れたとしても、損害賠償の請求は可能になります。
示談書に関するよくある疑問
Q. 示談書に決まった形式はありますか?
示談書に決められた形式は特にありません。用紙のサイズや枚数についても特に制限は設けられていません。用紙については、一般的にA4サイズが使われることが多いようです。また、枚数についても特に決まりはありませんが、複数枚になる場合には、割印を押しておくのがよいでしょう。割印を押すことで、複数の文書が同じ内容であることの証明にもなり、示談書の改ざんなどを防止することができます。
Q. 示談書は自分で作成できますか?
示談書は自分自身で作成することができます。交通事故の当事者同士が示談内容に合意していれば、当事者のどちらが示談書を作成しても、問題はありません。しかし、示談書は後々のトラブルを防ぐための重要な書類ですから、一度示談を結ぶと、原則として後から撤回や変更をすることはできません。記載内容の正確性も求められますので、少しでも不安がある場合には、弁護士などの専門家に相談しながら作成するようにしましょう。
Q. 交通事故の示談書は誰が用意すべきですか?
示談書を誰が用意するかといったことは、明確には決められていません。先述の通り、示談内容に合意していれば、示談書は当事者のどちらでも作成することができます。とはいえ、通常は加害者が任意保険に加入していれば、加害者側の保険会社が示談書を作成し、被害者に送付するというのが一般的な流れです。
後々のトラブル防止のために示談書の作成は大切
示談書とは、トラブルの解決方法を当事者間で話し合い、合意した内容をまとめた書類です。示談を行うことは、民法上の和解契約となるため、互いが約束した示談内容については、法的な拘束力があります。
示談書に署名・捺印した後は、原則として内容の撤回や変更はできません。そのため、示談書を作成することで、当事者間の合意内容が明確になり、後々のトラブルを防ぐことができます。合意内容を証明する書類として、示談書は重要な書類といえるでしょう。
示談書は決められた形式がないため、自ら作成することもできます。とはいえ、自分自身で相手方との交渉が必要になるため、手間や時間がかかります。当事者同士の話し合いでは、感情的になって紛争の解決が思うように進まないこともあるかもしれません。
このように、事故でダメージを受けている中で、自分自身が交渉を行うのは大きなストレスがかかります。任意保険に加入していれば、「対人賠償」「対物賠償」には保険会社の示談交渉サービスが付いているため、事故が発生した場合は、保険会社が示談交渉を行うことが一般的です。
交通事故は、普段から気をつけて運転していても、起きてしまうことも考えられます。事故が起きたときの示談交渉や示談書の作成で、保険会社のサポートが受けられることができれば、精神的にも大きな助けになるのではないでしょうか。
継続手続・2台目以降のお車の新規申込は、
ご契約者ページをご利用ください。
ご契約者の2台目以降の契約はマイページからの手続きがお得!
2台目以降はマイページ新規申込割引でさらに1,000円割引
※お支払回数によっては、記載の割引額 ちょうどにならない場合があります。
- インターネット割引12,000円※
- 24時間ネットで申込完結
- クレジットカード分割払OK
- 最短翌日から補償開始
※お支払回数によっては、記載の割引額ちょうどにならない場合があります。
ご契約者の方
自動車保険ガイド
- 自動車保険ガイド
- 代理店型保険会社からの乗換ガイド
- 補償内容の選び方
- 等級制度ガイド
- 契約手続の流れ
- 等級引継ぎガイド
- 車両保険ガイド
- 人気乗用車の保険料例
- トヨタ プリウスの保険料っていくら?
- ニッサン ノートの保険料っていくら?
- トヨタ アクアの保険料っていくら?
- トヨタ C-HRの保険料っていくら?
- ホンダ フリードの保険料っていくら?
- ホンダ フィットの保険料っていくら?
- トヨタ シエンタの保険料っていくら?
- トヨタ ヴィッツの保険料っていくら?
- トヨタ ヴォクシーの保険料っていくら?
- ニッサン セレナの保険料っていくら?
- トヨタ ルーミーの保険料っていくら?
- トヨタ カローラの保険料っていくら?
- スバル インプレッサの保険料っていくら?
- トヨタ タンクの保険料っていくら?
- ホンダ ヴェゼルの保険料っていくら?
- トヨタ ハリアーの保険料っていくら?
- トヨタ ノアの保険料っていくら?
- トヨタ パッソの保険料っていくら?
- ニッサン エクストレイルの保険料っていくら?
- スズキ ソリオの保険料っていくら?
- マツダ デミオの保険料っていくら?
- トヨタ ヴェルファイアの保険料っていくら?
- ホンダ ステップワゴンの保険料っていくら?
- トヨタ エスクァイアの保険料っていくら?
- トヨタ アルファードの保険料っていくら?
- マツダ CX-5の保険料っていくら?
- スズキ スイフトの保険料っていくら?
- トヨタ クラウンの保険料っていくら?
- ホンダ シャトルの保険料っていくら?
- マツダ アクセラの保険料っていくら?
- マツダ CX-8の保険料っていくら?
- スズキ クロスビーの保険料っていくら?
- 年代別の保険料相場
- 交通事故の過失割合
- 歩行者と四輪車の事故
- 青信号で横断歩道を渡る歩行者と赤信号無視の四輪車の事故
- 駐車スペース内での、歩行者と四輪車の事故
- 通路での歩行者と四輪車の事故
- 四輪車同士の事故
- 青信号車と赤信号車の事故
- 同幅員の交差点での事故
- 一方通行違反のある事故
- 方が明らかに広い道路での事故
- 一方に一時停止の規制がある道路での事故
- 交差する道路のうち一方が優先道路である場合
- 信号機のある交差点に、直進車・右折車ともに青信号で進入した場合の事故合
- 信号機のない交差点での事故
- 右折車が優先道路に出る場合の事故
- 道路外から道路に進入するために左折する場合
- センターオーバー
- 進路変更車と後続直進車の事故
- 転回(Uターン)中の車と直進車との事故
- 駐停車車両への追突事故
- 一方に一時停止の規制がある交差点での事故
- 進路変更車とゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故
- 交差点に進入した四輪車と緊急車両の事故
- 駐車場内の交差点での出会い頭の事故
- 駐車場内で駐車スペースから出る際に、前方通路を走る車と衝突
- 駐車場内の通路を進行する四輪車と、駐車スペースに進入しようとする四輪車の事故
- 駐車場内で、隣の駐車車両に接触・衝突
- 四輪車と二輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進四輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 赤信号で交差点に進入した直進二輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)
- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合)
- 四輪車に一時停止の規制がある場合の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合
- 信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故
- 四輪車と二輪車(バイク)のドア開放事故
- 二輪車(バイク)の駐停車車両への追突事故
- 信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車を巻込む事故
- 四輪車と自転車の事故
- 交差点に青信号で進入した自転車と、赤信号で進入した四輪車の事故
- 交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故
- 同程度の道幅の交差点での事故
- 広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故
- 広い道路からの四輪車と、狭い道路からの自転車の事故
- 四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
- 自転車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が優先道路を走行している場合
- 四輪車が一方通行を逆走している場合
- 自転車が一方通行を逆走している場合
- 同程度の道幅の交差点における「ながらスマホ」の自転車と四輪車の事故
- 前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の接触事故
- 高速道路での事故
- 四輪車同士の事故
- 四輪車が加速車線、二輪車が本線車道を走行中の事故
- 二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故
- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故
- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故(四輪車が走行車線、二輪車が追越車線)
- 前車の急ブレーキによる後続直進車の追突事故
- 歩行者と自転車の事故
- 横断歩道中の信号変更がない事故
- 横断歩道中の信号変更がある事故
- 歩行者が青信号で横断を開始した事故
- 歩行者が赤信号で横断を開始した事故
- 信号機の設置されていない横断歩道上の事故
- 車道通行が許されている場合の事故
- 車道通行が許されていない場合の事故
- よくある質問
- 過失割合全般
- 交通ルールについて
- 保険金のお支払いについて
- 自動車保険の自然災害ガイド
- 自動車保険の書類ガイド
- 自動車の税金ガイド
- 型式別料率クラスとは
- マンガでわかる自動車保険
- ご契約者ガイド
お問合せ
新規のお客様
0120-919-928
電話受付 9:00〜18:00
(平日・土日休日問わず)